「乱暴なチャージ(肩などで押す)」、「背後からのチャージ」、「なぐる」、
「おさえる」、「おす」、「ボールを手で扱う(ハンド)」です。

基本的な反則行為は「相手をける」、「つまずかせる」、「飛びかかる」、
「乱暴なチャージ(肩などで押す)」、「背後からのチャージ」、「なぐる」、
「おさえる」、「おす」、「ボールを手で扱う(ハンド)」です。

●「ハンド」
自陣のペナルティエリア内のゴールキーパーを除いて、選手がボールを手や腕で触れることです。
試合中に、"あっ!ハンドだ!"と思われるようなプレーに出会うことがあります。
しかし、ゴールキーパー以外の選手が試合中に悪質な意図をもってボールを手で扱うことは小学生では
まず考えられません。レフェリー(審判)の判定(ファウルとしても、しなくても)に従いましょう。
ちなみに強い勢いで飛んでくるボールが顔面や胴体に当るのをさけようとして、手が出た場合は「危険回避
行動」としてハンドとはみなされない場合が多いです。
●「オフサイド」
よくオフサイドルールが理解できないといわれますが、
オフサイドとは簡単にいえば相手の陣地深くまで入って、
相手選手の先まわりをしてボールを持っていてはいけない
ということ。つまり「待ち伏せ禁止」ということです。
ゴール前に攻撃側の選手が一人待っていて、そこへポーンと
ボールを蹴れば簡単に得点できるかもしれない。
しかし、それでは正々堂々と相手と勝負するという精神から
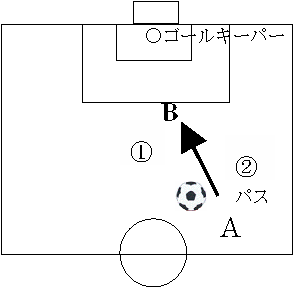
はずれてしまうからです。
簡単にオフサイドについて解説しますと、
右の図のように相手チームにゴールキーパーと①、②の3人がいる場合、ゴールラインから数えて2人目の①の位置がオフサイドライン(点線)になります。その①の選手より前にいるB選手が後ろのA選手からボールをもらうと(プレーに参加しようとしたら)オフサイドになります(1人目はちなみにボールキーパーです。1人目がかならずゴールキーパーとは限りません。例えば、このゴールキーパーが②の選手よりセンターライン側にいた場合、この時のオフサイドラインは②の位置になります)。オフサイドになる瞬間はA選手がボールを蹴った時点です。ですから、A選手がボールを蹴る前にB選手は①の選手の横(オフサイドライン)にいて、少しでも前にいなければオフサイドにはなりませんし、B選手がプレーの意志を示さなければ、これもオフサイドになりません。
また、A選手がドリブル(1人でボールを蹴って動かすこと)で相手ゴールに向かっていく場合、ボールを支配しているのがA選手なので、B選手がオフサイドポジション(点線より前にいる地点)にいてもオフサイドになりません。
ちょっと難しかったかな?
* 小学2年生以下のゲームでは「オフサイドルール」が適用されない場合がほとんどです。
●ファールスロー
スローインするとき小学生が非常に多い反則です。
・ ボールを投げるとき、足(片足でも)が地面から離れた場合。(出来るだけ遠くに飛ばしたいのと早く投げて味方に渡したいことから、足がおろそかになって離れてしまいます。実際は力を込めて上手くスロー出来た場合でも両足をしっかり固定してスローする場合も小学生では飛ぶ距離は1mも変わりませんし、急いでもそれほど時間が早くなるわけでもありません。しっかりとスローし、味方のボールにすることを心がけたいものですね)
・ ボールを投げるとき、頭を完全に通過しない場合。(よく頭を下げてスローする選手がいますが、これでは頭を完全に通過しないのでファールスローを取られてしまいます)
・ ボールを投げる方向と体の向きが違う場合。(気持ちは分かるのですが、投げようとしてからあっちに味方がいるので、あっちの味方に投げるの変更!とか、相手を欺こうとしてわざとそっち向いてあっちに投げよう!など選手自身で考え行動することはとても大切なことですが、反則です。上の頭を完全に通過できないのが主な理由ですが…)
・ タッチラインを踏み越えてスローした場合。(ラインを踏んでいるのはOK)
・ スローインする場所が1m以上離れて行われた場合。
●アドバンテージ
・ 反則行為がありました。しかし反則されたチームにとって有利にボールが展開しているとレフェリーが判断した場合はホイッスルを吹かず、そのまま試合を続行させることを「アドバンテージ」といいます。約2?3秒ほど待って、有利に展開しない場合、先ほどの反則の笛を鳴らしてプレーを止め、さっきの反則をとるために戻ります。有利に展開しているとそのままプレーを続行させます。この有利の考え方ですが、点に結びつくようなプレーと考えられていますが、有利に進んいるの判断やアドバンテージの時間については、レフェリーの判断で行われますので、その判断に従いましょう。
●プレーオン
・ プレー中、反則かな?どうかな?と思うようなプレーが起きた時、レフリーが反則でないと判断した場合にプレーを続けさせるため、レフェリーが両手を広げて「プレーオン」と合図をします。(プレーを続行させるためなのですが、たまにこのプレーオンのレフリーの声でプレーが止まってしまうことがあります(笑)。プレーは笛で止めますので、レフリーの声で止まらないでね)
参考資料
サッカーママ養成講座! http://www.geocities.co.jp/Athlete-Crete/4112/index.html
サッカー基礎編(池田書店)、ジャッジをくだす瞬間(講談社)